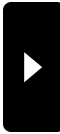2017年06月17日
伊豆88ヶ所霊場 区切り打ち通算7日目
休日を利用しランニングでのお遍路を一筆書きでやっています。
=前回の終了した地点からの再開です。
GWの3連続に続き、土日の晴天でまた行ってきました。
(実は5月27日と28日に、のレポです)
27日の土曜日は、前回終了の下田駅を起点で周回40km、
車中泊後の翌28日日曜日は下田から妻良あたりまで30kmほどを
廻る予定でした。
早朝 道の駅着、車をデポし下田駅へ向かいます。
下田駅7:30-広台寺-向陽院-米山寺-龍門院-報本寺-太梅寺-玄通寺-龍雲寺-曹洞寺-16:17下田駅
さてこの日は伊豆88お遍路の行程中で一番の難所?かと思われる、太梅寺から玄通寺までの
昔の遍路道を辿ります。
お遍路アプリにはそこを実際に歩いた足跡(ログ)が
あるので、GPSでそれを頼りに歩けばいいのですが、なにしろ地図には出て来ない
トレイルを行くもので、

国土地理院 1/25000の 地図を繋げ合わせますが
ルートは有りませんし、地図の破線を行こうとしても途中で
進めなくなっているらしいのです。
万一迷った場合のリスクが有りましたので、午前中に入山できなければ
諦めようと位に思っていました。
7:30に下田駅を出発し蓮台寺方面へ北上します。
44番札所 湯谷山 廣台寺
曹洞宗
御本尊真言は おん あろりきゃ そわか

8時ちょい前です..ちょっと時間が早いかと思ったけど、もう陽が高い季節なので
お邪魔しました。

かつては桂昌庵という真言宗の小さな庵でした。 1612(慶長17)年4月21日に現在地に移り、
曹洞宗に改宗、名も湯谷山廣台寺と改めました。
早い時間帯から暑い一日です
45番札所 三壺山 向陽院
臨済宗 (建長寺派)
御本尊真言は のうぼう あきゃしゃ きゃらばや おんありきゃ まりぼり そわか


1402(応永9)年に天台宗の阿闍梨が諸国行脚で河内を訪れ、
地蔵密庵と号した草庵を結び、虚空蔵菩薩(弘法大師作とか)と
地蔵菩薩を奉ったことが草創です。
46番札所 砥石山 米山寺
無属 (宗派に属さない)
御本尊真言は おん ころころ せんだり まとうぎ そわか

無住なので、この階段を上った建物でお参りしても良かったけど
山道を数百m登った山頂に奥の院があるそうなので
登っていきました。

所々急登も出てきますが何か所か標識が出て来て安心して進んでいけます。
明るく開けた場所に、ひっそりと奥の院 登場

733(天平5)年にこの地を訪れた行基が「寺を建てるのに良い所である」と言ったことから、
人々がその意に従い、程なくして寺が建てられたと伝えられています。
本尊の薬師如来も行基の作で、同年10月20日に入仏点眼し安置されたといいます。
ここでお作法をして、下山しましたが、下山の方が滑りやすくって大変かも..
お気をつけて
47番札所 保月山 龍門院
曹洞宗
御本尊真言は うまく さんまんだ ばざらだん せんだ まかろしゃだ そわたや
うんたらた かんまん
ながっ これを三辺お唱え...


ここも無住です
1099(康和元)年6月24日、保月嶽頂上の老松に光を放つ仏像が発見され、
龍が降臨すると言われていたこの地に庵を建てて安置することとなりました。
後に行脚の僧が「この像は青面金剛明王である」と言い、奉るようになりました。
当時は真言宗の寺院でしたが次第に衰退し、1593(文禄2)年に
太梅寺四世法山宗禅が復興して曹洞宗に改めました。
登り基調で大変でした
48番札所 婆娑羅山 報本寺
臨済宗 (建長寺派)
御本尊真言は おん あろりきゃ そわか

お留守でしたが、玄関に御朱印が置かれ、セルフで捺せるようになっています。
納経料300円はそこに収めます。
1323(元享3)年に富貴野山宝蔵院(第81番札所)に向かっていた真言宗成就院の阿闍梨が、
風岩峠付近でこの地が霊地であると感じ、1326(嘉暦元)年3月に婆娑羅山神護寺として
開堂しました。 しばらく無住の時期がありましたが、臨済宗として再興しました。
来た道を戻って太梅寺へ
良い天気過ぎて、、雨よりはいいけど 大汗
49番札所 神護山 太梅寺
曹洞宗
御本尊真言は おん かかかび さんまえい そわか

立派な山門が

お迎えしてくれますが

お留守
1046(寛徳3)年に行脚中の真言宗の僧が、この地に至った際に求めていた霊地だと感じ、
人々から浄財を集めお堂を建てました。 明星山満珠寺と名づけ、
地蔵尊を本尊として奉りました。 寺院の裏山には寺の鎮守として、稲荷神社が勧請されました。
後に寺名を改めて太梅山深居庵とし、臨済宗に改宗しました。
更にその後の1557(弘治3)年には曹洞宗に改宗し寺院名は深居山太梅寺となり、
1852(嘉永5)年に現在の山号に変わったと伝えられています。
11:30 予定通り旧お遍路道を辿るために、山へ入っていきます。
まずは林道ですが、しばらく行くと、やはり地図上の道からは外れていきます。
なのでここから先はお遍路アプリの足跡を辿っていく形になります。
とはいえ、上の見通しが悪い箇所などではGPSが所々で飛んでしまい、
明らかに道が続いてれば進みますが、踏み跡がハッキリしない個所では、現在地確認
(現在地がアプリの足跡近くに戻る)のために、しばらく立ち止まるかウロウロします。

トレイルを辿れるうちは良いのですが、


山慣れしていない方は、十分時間的マージンをもって、また単独でなく複数人で
行かれるなどお気をつけて。。
けっこう心細くなるほどの不明瞭な場所も有ったり
フェイントのように、ここ行くの? みたいな分岐も有ったり

自分は通過に1:50ほど掛かりました...

県道に出て一安心
50番札所 吉松山 玄通寺
曹洞宗
御本尊真言は おん あろりきゃ そわか

頑張って辿り着くも残念ながら無住

かつては下田市との境にある小松野山の頂にありましたが、
何度もの火災に遭い記録が焼失しているため、創建年等は一切不詳となっています。
しかし開山の玄翁心昭が1396(応永3)年に入寂していることから、
草創はそれ以前と考えられます。 1911(明治44)年に庫裏が、翌年に本堂が現在地に移されました。
かなり疲れてきました
51番札所 青谷山 龍雲寺
曹洞宗
御本尊真言は おん あみりた ていぜい から うん

ここも残念ながら無住ですが

長谷寺で御朱印が頂けると..有難い情報です。
1284(宝治2)年に真言宗の寺院として創建されました。
永禄年間(1558~1570年)に曹洞宗に改宗となりました。
ラストスパート
52番札所 少林山 曹洞院
曹洞宗
御本尊真言は おん あびらうんけん ばざら だどばん

ちょっと最後の登りがきつかったけど

こちらでは有難いことにお茶を入れて頂き、地元のお菓子も..
伊豆では珍しいと思うのですが、緑茶でした。
(昔から伊豆ではホテルなんかでもほうじ茶がメインというイメージ、緑茶飲んだ覚えがほとんどなし)
美味しくって、すぐに飲み干し..一杯だけでなく、急須ごと出して頂いちゃいました。
ここのご住職は良いお歳なのですが、若かりし頃はマラソンを
やっていたそうです。
さてさて15:30
下田駅へ急ぎましょう
汗一杯かいたからどこの温泉に行こうかなと、そればかり考えてました。
下田駅でログを切って、道の駅までダウンジョグでほんとの終了。

写真では判らないですが、お遍路中はランシャツの上に袖なし白衣と輪袈裟を着けて
走っていまして、それも汗まみれですが。。。選択するすべがなく
翌日もそのままです。
一応飛ばされないように車に引っ掛けて干しましたが。
結構こまごまとお金使っているので、お風呂も安いところを探しまして、
その名も 昭和湯 さん 400円 ですが

うん 入り口はいるとすぐに脱衣所でその向こうは浴室。

休憩するようなスペースなし。
また浴室には石鹸、シャンプー無しで番台で40円で購入できます。
常連さんは脱衣所の上の棚に、マイ石鹸/マイシャンプーをキープしていました。
そしてシャワーも無しです。
浴槽はおへそ位の深さが有り、しゃがめない(笑)
浴槽の縁に辛うじて10cm位の段差があり、そこにお尻を引っ掛けて
中腰で寄りかかりながら浸かるって感じでした。
いや、まあこんなのも有りかと、実は翌日も逝っちゃいましたよ(笑)
節約ついでに、夕食はスーパーでお惣菜やビールなどを買い込み
お寿司パックも買って道の駅へ戻り、

車外でテーブルとチェアを出して食べて飲んでマッタリしていましたが、
風もちょっと涼しく、1時間もすると寒くなってきたり。
駐車スペースへ移動し、翌日に備えて21時頃には寝る体制でした。
=前回の終了した地点からの再開です。
GWの3連続に続き、土日の晴天でまた行ってきました。
(実は5月27日と28日に、のレポです)
27日の土曜日は、前回終了の下田駅を起点で周回40km、
車中泊後の翌28日日曜日は下田から妻良あたりまで30kmほどを
廻る予定でした。
早朝 道の駅着、車をデポし下田駅へ向かいます。
下田駅7:30-広台寺-向陽院-米山寺-龍門院-報本寺-太梅寺-玄通寺-龍雲寺-曹洞寺-16:17下田駅
さてこの日は伊豆88お遍路の行程中で一番の難所?かと思われる、太梅寺から玄通寺までの
昔の遍路道を辿ります。
お遍路アプリにはそこを実際に歩いた足跡(ログ)が
あるので、GPSでそれを頼りに歩けばいいのですが、なにしろ地図には出て来ない
トレイルを行くもので、

国土地理院 1/25000の 地図を繋げ合わせますが
ルートは有りませんし、地図の破線を行こうとしても途中で
進めなくなっているらしいのです。
万一迷った場合のリスクが有りましたので、午前中に入山できなければ
諦めようと位に思っていました。
7:30に下田駅を出発し蓮台寺方面へ北上します。
44番札所 湯谷山 廣台寺
曹洞宗
御本尊真言は おん あろりきゃ そわか

8時ちょい前です..ちょっと時間が早いかと思ったけど、もう陽が高い季節なので
お邪魔しました。

かつては桂昌庵という真言宗の小さな庵でした。 1612(慶長17)年4月21日に現在地に移り、
曹洞宗に改宗、名も湯谷山廣台寺と改めました。
早い時間帯から暑い一日です
45番札所 三壺山 向陽院
臨済宗 (建長寺派)
御本尊真言は のうぼう あきゃしゃ きゃらばや おんありきゃ まりぼり そわか


1402(応永9)年に天台宗の阿闍梨が諸国行脚で河内を訪れ、
地蔵密庵と号した草庵を結び、虚空蔵菩薩(弘法大師作とか)と
地蔵菩薩を奉ったことが草創です。
46番札所 砥石山 米山寺
無属 (宗派に属さない)
御本尊真言は おん ころころ せんだり まとうぎ そわか

無住なので、この階段を上った建物でお参りしても良かったけど
山道を数百m登った山頂に奥の院があるそうなので
登っていきました。

所々急登も出てきますが何か所か標識が出て来て安心して進んでいけます。
明るく開けた場所に、ひっそりと奥の院 登場

733(天平5)年にこの地を訪れた行基が「寺を建てるのに良い所である」と言ったことから、
人々がその意に従い、程なくして寺が建てられたと伝えられています。
本尊の薬師如来も行基の作で、同年10月20日に入仏点眼し安置されたといいます。
ここでお作法をして、下山しましたが、下山の方が滑りやすくって大変かも..
お気をつけて
47番札所 保月山 龍門院
曹洞宗
御本尊真言は うまく さんまんだ ばざらだん せんだ まかろしゃだ そわたや
うんたらた かんまん
ながっ これを三辺お唱え...


ここも無住です
1099(康和元)年6月24日、保月嶽頂上の老松に光を放つ仏像が発見され、
龍が降臨すると言われていたこの地に庵を建てて安置することとなりました。
後に行脚の僧が「この像は青面金剛明王である」と言い、奉るようになりました。
当時は真言宗の寺院でしたが次第に衰退し、1593(文禄2)年に
太梅寺四世法山宗禅が復興して曹洞宗に改めました。
登り基調で大変でした
48番札所 婆娑羅山 報本寺
臨済宗 (建長寺派)
御本尊真言は おん あろりきゃ そわか

お留守でしたが、玄関に御朱印が置かれ、セルフで捺せるようになっています。
納経料300円はそこに収めます。
1323(元享3)年に富貴野山宝蔵院(第81番札所)に向かっていた真言宗成就院の阿闍梨が、
風岩峠付近でこの地が霊地であると感じ、1326(嘉暦元)年3月に婆娑羅山神護寺として
開堂しました。 しばらく無住の時期がありましたが、臨済宗として再興しました。
来た道を戻って太梅寺へ
良い天気過ぎて、、雨よりはいいけど 大汗
49番札所 神護山 太梅寺
曹洞宗
御本尊真言は おん かかかび さんまえい そわか

立派な山門が

お迎えしてくれますが

お留守
1046(寛徳3)年に行脚中の真言宗の僧が、この地に至った際に求めていた霊地だと感じ、
人々から浄財を集めお堂を建てました。 明星山満珠寺と名づけ、
地蔵尊を本尊として奉りました。 寺院の裏山には寺の鎮守として、稲荷神社が勧請されました。
後に寺名を改めて太梅山深居庵とし、臨済宗に改宗しました。
更にその後の1557(弘治3)年には曹洞宗に改宗し寺院名は深居山太梅寺となり、
1852(嘉永5)年に現在の山号に変わったと伝えられています。
11:30 予定通り旧お遍路道を辿るために、山へ入っていきます。
まずは林道ですが、しばらく行くと、やはり地図上の道からは外れていきます。
なのでここから先はお遍路アプリの足跡を辿っていく形になります。
とはいえ、上の見通しが悪い箇所などではGPSが所々で飛んでしまい、
明らかに道が続いてれば進みますが、踏み跡がハッキリしない個所では、現在地確認
(現在地がアプリの足跡近くに戻る)のために、しばらく立ち止まるかウロウロします。

トレイルを辿れるうちは良いのですが、


山慣れしていない方は、十分時間的マージンをもって、また単独でなく複数人で
行かれるなどお気をつけて。。
けっこう心細くなるほどの不明瞭な場所も有ったり
フェイントのように、ここ行くの? みたいな分岐も有ったり

自分は通過に1:50ほど掛かりました...

県道に出て一安心
50番札所 吉松山 玄通寺
曹洞宗
御本尊真言は おん あろりきゃ そわか

頑張って辿り着くも残念ながら無住

かつては下田市との境にある小松野山の頂にありましたが、
何度もの火災に遭い記録が焼失しているため、創建年等は一切不詳となっています。
しかし開山の玄翁心昭が1396(応永3)年に入寂していることから、
草創はそれ以前と考えられます。 1911(明治44)年に庫裏が、翌年に本堂が現在地に移されました。
かなり疲れてきました
51番札所 青谷山 龍雲寺
曹洞宗
御本尊真言は おん あみりた ていぜい から うん

ここも残念ながら無住ですが

長谷寺で御朱印が頂けると..有難い情報です。
1284(宝治2)年に真言宗の寺院として創建されました。
永禄年間(1558~1570年)に曹洞宗に改宗となりました。
ラストスパート
52番札所 少林山 曹洞院
曹洞宗
御本尊真言は おん あびらうんけん ばざら だどばん

ちょっと最後の登りがきつかったけど

こちらでは有難いことにお茶を入れて頂き、地元のお菓子も..
伊豆では珍しいと思うのですが、緑茶でした。
(昔から伊豆ではホテルなんかでもほうじ茶がメインというイメージ、緑茶飲んだ覚えがほとんどなし)
美味しくって、すぐに飲み干し..一杯だけでなく、急須ごと出して頂いちゃいました。
ここのご住職は良いお歳なのですが、若かりし頃はマラソンを
やっていたそうです。
さてさて15:30
下田駅へ急ぎましょう
汗一杯かいたからどこの温泉に行こうかなと、そればかり考えてました。
下田駅でログを切って、道の駅までダウンジョグでほんとの終了。

写真では判らないですが、お遍路中はランシャツの上に袖なし白衣と輪袈裟を着けて
走っていまして、それも汗まみれですが。。。選択するすべがなく
翌日もそのままです。
一応飛ばされないように車に引っ掛けて干しましたが。
結構こまごまとお金使っているので、お風呂も安いところを探しまして、
その名も 昭和湯 さん 400円 ですが

うん 入り口はいるとすぐに脱衣所でその向こうは浴室。

休憩するようなスペースなし。
また浴室には石鹸、シャンプー無しで番台で40円で購入できます。
常連さんは脱衣所の上の棚に、マイ石鹸/マイシャンプーをキープしていました。
そしてシャワーも無しです。
浴槽はおへそ位の深さが有り、しゃがめない(笑)
浴槽の縁に辛うじて10cm位の段差があり、そこにお尻を引っ掛けて
中腰で寄りかかりながら浸かるって感じでした。
いや、まあこんなのも有りかと、実は翌日も逝っちゃいましたよ(笑)
節約ついでに、夕食はスーパーでお惣菜やビールなどを買い込み
お寿司パックも買って道の駅へ戻り、

車外でテーブルとチェアを出して食べて飲んでマッタリしていましたが、
風もちょっと涼しく、1時間もすると寒くなってきたり。
駐車スペースへ移動し、翌日に備えて21時頃には寝る体制でした。
Posted by nai at 23:01│Comments(0)
│伊豆88